【名著】実存主義とは何か|サルトル 人生がうまくいく人の、超単純な共通点について ~20世紀最大の哲学者が語る、希望の哲学~
📅 2023年12月19日
この動画で紹介されたおすすめ商品(5個)

実存主義とは何か
おすすめコメント
ジャン=ポール・サルトルの代表作『実存主義とは何か』は、1945年の伝説的講演をまとめた実存主義の入門書と紹介されています。第2次大戦後の人々に希望を与え、世界を熱狂させた思想のエッセンスが押さえられていると説明されています。
- •実存主義の中核概念として、「実存は本質に先立つ」、「人間は自由の刑に処せられている」が示されると紹介されています。
- •自らの選択と行動で自己を形成し、全人類への責任を引き受ける姿勢が強調されているそう。
- •「人間とは自分の行動の総体である」という視点が提示され、決定論的な見方への批判も語られていると説明されています。
- •他者のまなざしへの向き合い方や、アンガージュマン(自由な社会的関与)の重要性にも触れられているだとか。
- •講演に対する諸批判への応答と、実存主義の概略が整理されていると紹介されています。
おすすめの読者
- •哲学思想に興味のある人
- •自由に生きる方法を探している人
- •何者にもなれないという呪縛から解放されたい人
- •他人の評価が気になりやすい人
- •行動力を身につけ夢や目標に一歩近づきたい人
サルトルの生涯や他作品にも触れつつ、本書の要点がわかりやすく整理されていると紹介されています。

嘔吐 新訳
おすすめコメント
- •『嘔吐 新訳』は、ジャン=ポール・サルトルによる1938年発表の小説で、実存主義の重要作のひとつと紹介されています。
- •作中の主人公ロカンタンが美術館で肖像画の重い視線を受ける場面が引用され、他者のまなざしへの対処のヒントが示されていると紹介されています。
- •一方的に視線を受けるのではなく、こちらからも視線を向けることで多重化を防ぎ、主体性を守る態度が描かれているそう。
- •生身の人間関係にも応用でき、否定的な評価を一方的に飲み込まず「視線を受け返す」ことで自己を保つ示唆が得られる本だとか。
他人の評価が気になりがちな人に、他者の視線に揺さぶられないための実践的な手がかりが得られると紹介されています。
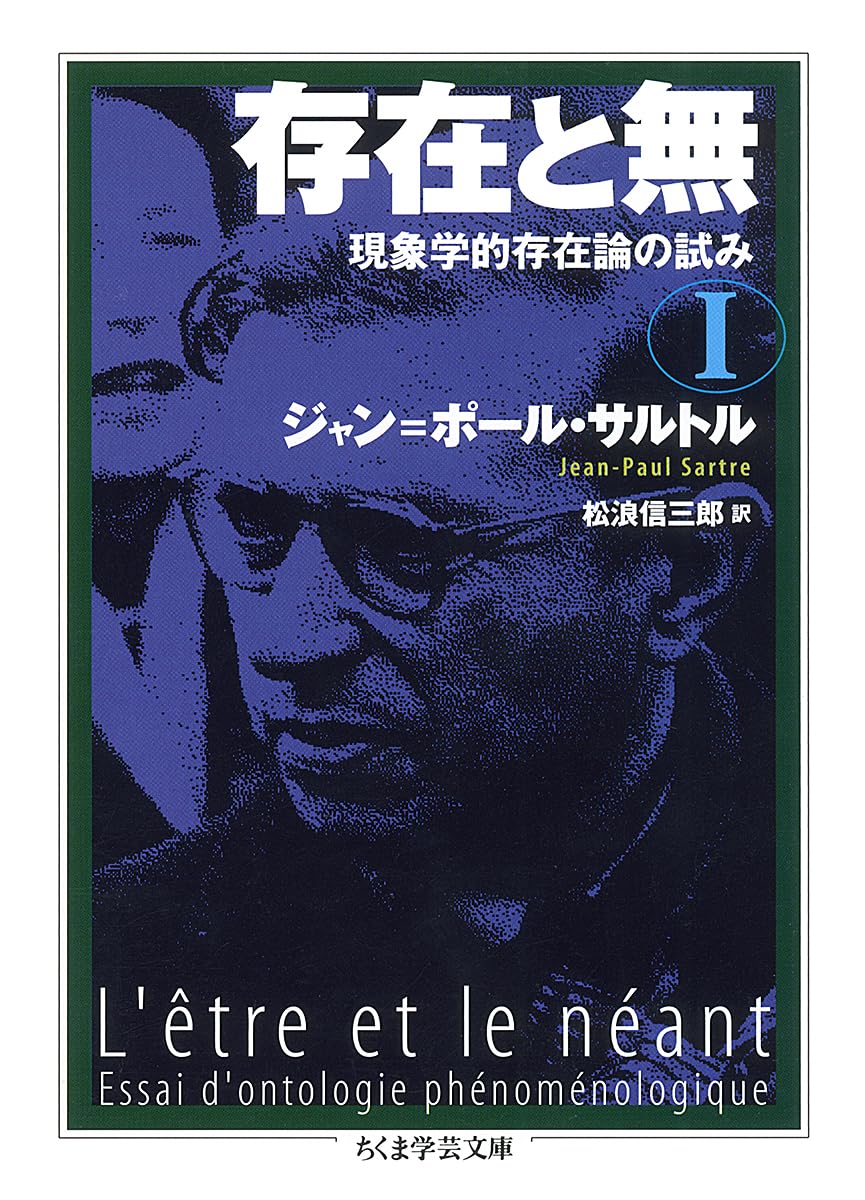
存在と無: 現象学的存在論の試み (1) (ちくま学芸文庫 サ 11-2)
おすすめコメント
1943年刊行のサルトルの代表作『存在と無』と紹介されています。実存主義ブームの火付け役となり、哲学書としては異例の売上を記録、フランス全土に大きな衝撃を与えたそう。サンジェルマン=デ=プレの若者文化と結びつき、実存主義への賛否を呼ぶきっかけになっただとか。
- •フッサールの現象学に惹かれた後に刊行された流れで紹介されています。
- •実存主義ブームの中心として語られ、思想的インパクトの大きさが強調されているそう。
- •パリのサンジェルマン=デ=プレで若手知識人が集い、議論が活発化した文脈とともに位置づけられているとされています。
- •カフェ・ド・フロールでの執筆や議論のエピソードと併せて言及され、当時の文化的熱気を象徴する書だとか。
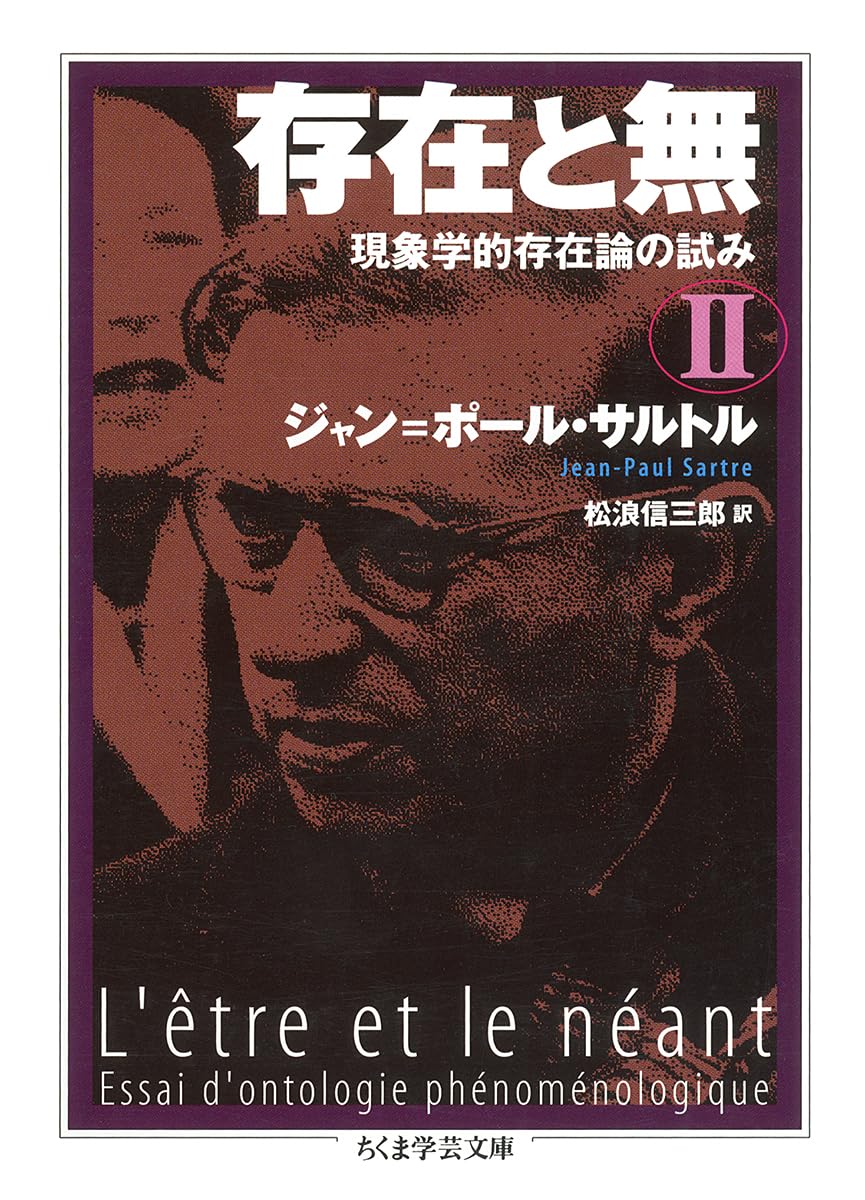
存在と無: 現象学的存在論の試み (2) (ちくま学芸文庫 サ 11-3)
おすすめコメント
1943年刊行の『存在と無』が、実存主義ブームの火つけ役となり、哲学書としては異例の売上を記録、フランス全土に大きな衝撃を与えたと紹介されています。特にサンジェルマンデプレで若い文学者や哲学者の間に広まり、議論の中心になったそう。
- •カフェフロールで執筆に励み、「サンジェルマンデプレの王」と慕われたエピソードとともに語られているとか。
- •若者たちの奔放なイメージとも結びつき、実存主義への批判が生まれるきっかけにもなったと説明されています。
- •サルトルの思想の文脈では、「実存は本質に先立つ」、「人間は自由の刑に処せられている」、責任と行動、他者のまなざし、アンガージュマンといったキーワードが丁寧に解説されているそう。
- •入門には講演をまとめた『実存主義とは何か』が紹介されており、その理解を踏まえて本書に向かう流れが示されていると紹介されています。
サルトルの思想が、現代の生きづらさや他人の評価との向き合い方にヒントを与える文脈で語られており、『存在と無』の位置づけがよく伝えられているだとか。

存在と無: 現象学的存在論の試み (3) (ちくま学芸文庫 サ 11-4)
おすすめコメント
1943年刊行の『存在と無』。実存主義ブームの火付け役となり、哲学書としては異例の売上を記録、フランス全土に大きな衝撃を与えたと紹介されています。
- •オーストリアの哲学者フッサールの現象学に魅了され、研究ののちに執筆された代表作だとか。
- •パリのサン=ジェルマン=デ=プレの若者文化と結びつき、実存主義へのさまざまな批判が生まれるきっかけになったそう。
- •サルトル思想の核として、「実存は本質に先立つ」、「人間は自由の刑に処せられている」、責任と行動、他者のまなざし、アンガージュマンといったテーマが取り上げられていると説明されています。
- •サルトルを理解するうえで欠かせない中心的著作と位置づけられているとか。
Amazonのアソシエイトとして、当サイトは適格販売により収入を得ています。